初めに
こんにちは!シミュレーション技法研究室に所属しているゆうき(@engieerblog_Yu)です。
やっと卒論に向けての研究が終了したので、今回は卒論の内容のパターンとその構成について解説していきたいと思います!
卒論の内容
卒論の内容は大きく分けて以下です。
既存の手法を改善
既存の手法を異なる分野に適応
新しい手法を開発

それぞれ解説していきます。
既存の手法を改善
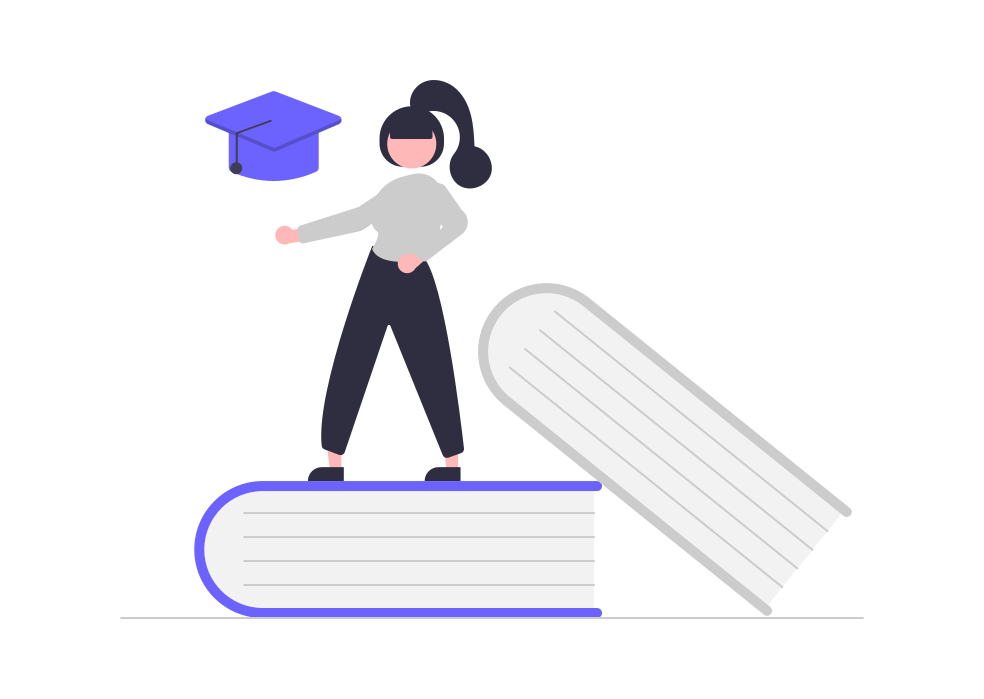
卒論の内容の中で、最も多いものが既存の手法を改善するというものです。
既存の手法とは、主に以下の二つです。
arxivなどに出版されている論文にある手法
同じ研究室内の先輩がやってきた手法
それぞれを用いるメリットとデメリットがあります。
メリット
既に出版されている論文にある手法→審査に通っているので、ある程度のクオリティが保証されている
先輩がやってきた手法→研究の筋道がはっきりしやすく、質問しやすい
デメリット
既に出版されている論文にある手法→レベルが高いため、議論の抜けが少なく、改善するのが難しい
先輩がやってきた手法→実験が終了した時点で、議論の抜けがある可能性がある
研究室内の先輩がやってきた手法に乗っかるのが、研究としては比較的楽だと思います。
論文にある手法を用いると、
論文を読んで完璧に理解する→問題を発見する→論文の手法が使えないか検証する
というサイクルが必要です。
しかし、一通り実験が終わった段階で、で?結局何がいいの?別の手法で良くない?という結論になりがちです。
私の場合は、論文にある手法を用いていますが、教授と何度も話して方向性を決めても、一回ボツになりました。
常にどのようなストーリーで研究を進めていくのか、考え続けていくことが大切だと思います。
研究は、常にどのようなストーリーで研究を進めていくのか、考え続けていくことが大切
既存の手法を異なる分野に適応
次に既存の手法を異なる分野に適応していくという例です。
これも先ほどの論文や先輩がやってきた手法が対象です。
例えば、n次元データの特徴を解析して、二次元空間にプロットするという基盤があったとします。
今までの実験では、気象のデータにしか適応した例がなかったとします。
そこで全く異なる心理学のデータなどに適応して、妥当性を検証する、といったことです。
既存の手法を異なる分野に適応していくのは、大体解釈が難しくなることが多いです。
元々の手法が、異なった分野に対応していなかった場合、よくわからない結果が出てくることになります。
基盤の中身の変更や、出てきた結果をどう解釈するのかが大切になると思います。
既存の手法を異なる分野に適応する場合、基盤の中身の変更や、出てきた結果をどう解釈するのかが大切
新しい手法を開発
卒論の内容の中で、最も難しいものが新しい手法を開発するということです。
正直0から新しい手法を作ったというのは、あまり聞いたことがないです。
新しい手法を作るというのは、何十年も研究してきた研究者の研究と比較して、どうしてもクオリティが低くなりがちです。
コスパとクオリティを考えて、既存の手法を扱う人がほとんどだと思います。
前提知識が研究者並みにあり、情熱を持った人ならばできるかもしれません。
論文の構成(IMRaD)
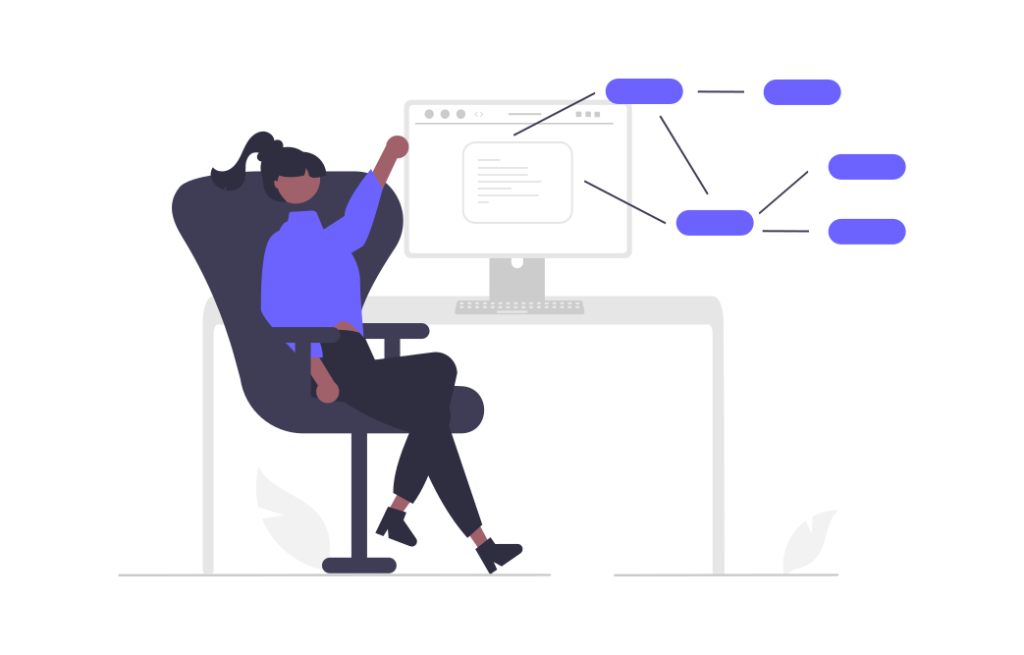
論文の構成はIMRaDで構成されていることが多いです。
IMRaDとは、以下の英単語の頭文字を取っています。
Introduction(導入)
Method(手法)
Results(結果)
Discussion(考察)
簡単で当たり前のように思えますが、これが結構難しいです。
かなり簡単にまとめると、
導入で、自分の研究分野の状況や自分の研究の位置づけを行う。
手法を説明し、結果についても説明する。
考察では結果を要約し、目的を振りかえる。その後研究の限界や問題点を示す。
となります。
手法と結果についてがメインになってしまい、導入と考察が疎かになってしまうことが多い印象があります。
常に何のためにこの研究を行っているのか?結果から何が分かって、どうすれば目的を達成できるのか?について考え続けることが大切です。
以下の記事で、IMRaDについて、より詳しくまとめているので合わせてどうぞ。
終わりに
今回は工学部の卒論の内容と構成について、かなり簡単にまとめてみました。
研究とは、どんなことをしているのか少しはイメージしていただけたら嬉しいです!
他にも実際の研究内容や研究の面白さについても記事を出しているので、そちらもよかったら。


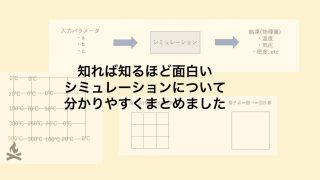
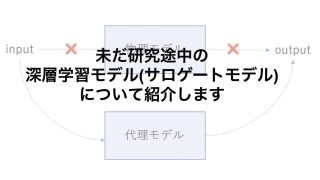

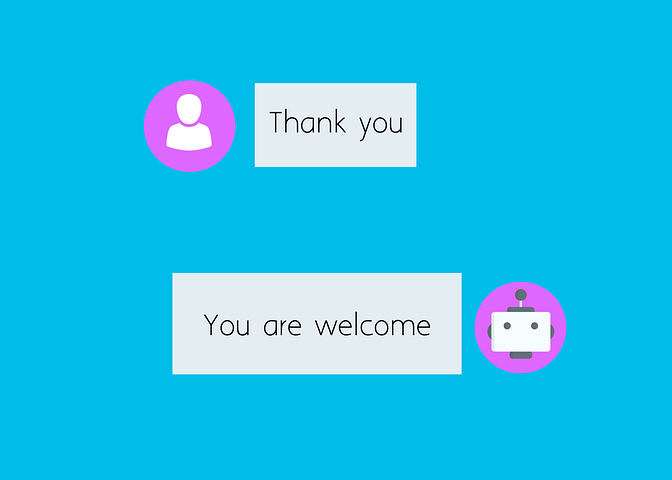
コメント