どーも、ゆうき(@engieerblog_Yu)です。
突然ですが、先日プラネタリウムに行った時の話です。
プラネタリウムの解説員の方が、3択問題を出していました。
「今まで人類で火星に行ったのは何人でしょうか?」
1.一人
2.三人
3.五人
「暗くて見えないので拍手で答えてください。」
私は月でもそんなに行けてないのに火星に何人も行けるわけがないと思い、3人のところで拍手をしました。
大体の人が3人あたりで拍手をしていたように思えます。
しかし正解は選択肢にない、0人でした。
騙されたと思い、その日は家に帰ったのですが、今回紹介する認知バイアス辞典を読んでいると、
人間には、事前に持っている情報に基準を左右されてしまう認知バイアスがあることを知りました。
つまり、一人~五人という選択肢が出された時点で、私たちは無意識のうちに「火星に行った人がいる」と錯覚してしまったわけです。
どうやらこれはアンカリングというらしいです。
このように私たちは気づかないうちに、無意識で正しくないバイアスをかけてしまう傾向があります。
このような認知バイアスを放っておくと、、、
人間関係、貯蓄、日常にある一つ一つの選択で、損をする
騙される
他人の認知バイアスに気づかずに、自分も影響を受けてしまう
ということが気づかないうちに起こります。
今回紹介する認知バイアス辞典は、そのようなバイアスによって、損をしないための一冊です。
本書には、先ほど紹介したアンカリングに加えて、60種類の認知バイアスが紹介されています。
本書を読むことによって、以下の効果があります。
行動経済学・統計学・情報学に基づいた、認知バイアスを減らして、損をしないための行動を知ることができる
認知バイアスを利用する悪い人間に騙されない
支出を減らして貯蓄を増やすことができる
客観的に物事を判断できるようになる
気づかないうちに損をしたくない!という方に、おすすめの一冊です。
本書で特に面白かった認知バイアスについて紹介しますね。
シンプソンパラドックスについて
シンプソンパラドックスとは、本書で以下のように定義されています。
ある集団全体の傾向と、その集団をいくつかのグループに分割したときの傾向が異なる現象。
認知バイアス辞典(行動経済学・統計学・情報学編)より
例えば、A高校の模試の平均点が70点だったとします。
B高校の模試の平均点は65点です。
人数はどちらも同じで200人だとします。
するとほとんどの人は、B高校よりもA高校の方が成績が良いと考えるでしょう。
しかし、これを文系と理系で分けてみると
A高校は、文系の平均点は75点(150人)、理系の平均点は55点(50人)
B高校は、文系の平均点は80点(50人)、理系の平均点は60点(150人)でした。
A高校はただ単に、平均点が高い文系の人数が多かったから、全体の平均点が高かったのです。
つまり全体の平均点が高い→成績が良いというのは必ずしも成立するとは限らないという訳です。
このように、シンプソンパラドックスでは、集団の傾向とグループの傾向が異なることで、誤った解釈をしてしまう可能性があります。
本書では、このような面白い認知バイアスが他にも60種類まとめてあります。
人生の早いうちに知っておくと、損をしなくて済むと思います。
こちらも面白かったので合わせておすすめです。。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

他にもいろんな記事があるにゃ。


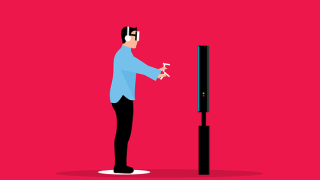


コメント